ソルリスカイウォーク(설리스카이워크)
2023-02-15
キョンサンナム道ナムヘ郡ミジョ面ミソンロ303ボンギル176
慶尚南道(キョンサンナムド)南海郡(ナムヘグン)弥助面(ミジョミョン)に位置しているソルリスカイウォークは円筒型構造で、360度どの方向からも南海を見渡すことができます。韓国初の「非対称カンチレバー橋」として建てられたスカイウォークは、高さ約36メートルに幅4.5メートル、総延長79メートルで、片端は固定し別の片端は支持されていない「カンチレバー」構造となっています。このソルリスカイウォークは43メートルで韓国内で最も長いカンチレバー構造物といえます。また「スウィングブランコ」はインドネシアバリ島の名物、「バリスウィング」をモチーフに製作され、高さ38メートルのスカイウォークの端でスリルを満喫できます。
壮子島(장자도)
2025-11-28
チョンブク特別自治道クンサン市オクト面チャンジャド1ギル26-2
古群山(コグンサン)群島の一つで、壮士(力持ち)が生まれたということから壮子島(チャンジャド)と名付けられました。海で操業中に突然嵐に遭ったとき、この島に避難すれば安全だということで、避難港として知られています。仙遊島(ソニュド)とは壮子橋でつながっています。 壮子島は古郡山群島の中央に位置しており、テジャン峰に登ると、古群山群島の63の島々が視界に広がり、韓国山岳会、韓国写真作家協会、3社の放送局からベストショットスポットとして選ばれています。干潟体験、海釣り、海上釣りなどのレジャー活動が可能で、活魚の刺身、海鮮の蒸し物、アサリカルグクス、イシガニのケジャンなど、海鮮を利用したグルメが豊富で、さらに日の出・日没スポット、テジャン峰登山、ハイキング、古群山群島の遊覧船観光、夕日の壮観が見られる壮子大橋、壮子ハルモニ岩、大長島堂祭など、多くの観光スポットがあり、夏のシーズンでなくても観光に適した場所です。
仙遊島海水浴場(선유도해수욕장)
2025-11-27
チョンブク特別自治道クンサン市オクト面
全羅北道(チョンラブクド)群山市(クンサンシ)沃島面(オクトミョン)に位置する仙遊島(ソニュド)海水浴場は、天然の海岸砂丘の海水浴場で、ガラスのように透明感のある美しい白い砂浜が広がっているため、明沙十里(ミョンサシムニ)海水浴場とも呼ばれています。仙遊島海水浴場は、100メートル以上進んでも水深が大人の腰までしかこない遠浅で、高波がなく、安心して海水浴が楽しめます。
秘密の森(비밀의 숲)
2025-10-28
チェジュ特別自治道チェジュ市クジャ邑ソンダン里2173
済州(チェジュ)市旧左(クジャ)邑に位置している秘密の森は、ソーシャルネットワークでフォトスポットとして有名になりました。他の有名な榧子林(ピジャリム)やサリョニ森の道とは違った魅力があります。希少なヒノキの森や広い草原、石垣や小屋など多彩な構成で、済州島ならではの雰囲気を持つフォトスポットが満載です。とくに菜の花やピンクミューリー(ミューレンベルギア・カピラリス)など、四季折々の美しい自然を楽しむことができます。ただ、私有地のため入場前の撮影は不可で、舗装道路へ行くにはホームページに載っている住所を参考にする必要があります。
天津港(천진항)
2023-01-26
チェジュ特別自治道チェジュ市ウド面ヨンピョン里1737-15
済州(チェジュ)の東端にあり、一番先に日が昇る島であるとともに済州に付属する島の中で最も大きな牛島(ウド)は、見どころ・食べどころ・楽しみどころが満載で、いつも観光客でにぎわう観光スポットです。歩いて移動するには広すぎるので、島に自動車を持ち込むか、または現地で電動スクーターや小型EV、バスの利用をおすすめします。牛島には船着場が2ヶ所あります。天津(チョンジン)港と下牛目洞(ハウモクトン)港です。天津港は牛島の玄関口となる港で、電動スクーターなどのレンタル業者が多いため、たいていの観光客はここで降ります。城山(ソンサン)港や終達(チョンダル)港から天津港までは10分~15分ほどかかります。
ソミ庭園(섬이정원)
2023-01-30
キョンサンナム道ナムヘ郡ナム面ナムミョンロ1534-110
ソミ庭園は南海に位置する閑麗(ハンリョ)海上国立公園の美しい海が見下ろせる棚田の古い石垣と池、そして生垣に多様な草やススキで演出したフォーマルで自然美のある欧州風の庭園です。高さの異なる棚田を利用して9つの小さな庭園が部屋のように分離し、それぞれが個性にあふれ、ときにはそれらが調和して特別な風景を作り出し、人々の目を楽しませてくれます。
南海宝島展望台(남해보물섬전망대)
2023-01-20
キョンサンナム道ナムヘ郡サムドン面トンブデロ720
南海宝島(ナムヘ・ポムルソム)展望台は韓国最南端の「南海」を美しく照らす灯台の様子を形象化した建築です。内部から眺める海の景色は豪華なクルーズに乗っているかのような、360度パノラマの海が眺望できます。2階の「スカイウォーク」ではガラス張りの空の道を歩いて、崖から素敵な南海を一目で見下ろし、美しい南海の日の出と日没、月の出を楽しめます。
金海盆山城(김해 분산성)
2024-02-05
キョンサンナム道キムヘ市カヤロ405ボナンギル210-162
盆山城(プンサンソン)は洛東江下流の広い平野を一望できる盆山の頂上に周囲約900メートルにわたって石で積み上げられた山城です。初めて築城された年代は定かではありませんが、三国時代と推定されています。
山頂にある平坦な地形を囲んでその周囲に南北に長い楕円形を成した城壁で、垂直に近い石壁は高さ約3~4メートルで崩れた部分が少なくありません。ここに建てられた「靖國君朴公葳築城事蹟碑」によると、この山城は朝鮮初期に朴葳(パク・ウィ)が古山城に基づいて修築した後、壬辰倭乱時に崩れたものを1871年(高宗8年)に再度修理したということです。
金海(キムヘ)市内、金海平野と洛東江(ナクトンガン)、そして南海を一目で見渡せる盆山(プンサン)の頂上部に帯を締めるような形で石を積んだ山城で、現在は市内側の傾斜面に900メートル程度の城壁が残り、城内には南北に2つの門址と西側の暗門、井戸跡などいくつかの建築跡もみかけられます。城郭の総延長は929メートル、幅は平均約8メートルです。 山城の中には海恩寺(ヘウンサ)があります。
盆山城の別名、万丈台(萬丈臺)
金海市民たちには「万丈台(マンジャンデ)」という名称がより親しみがありますが、それは朝鮮時代に大院君が倭を退ける前進基地として「万丈もある高い台」という名前をさずけたことがその起源となっています。1999年に復元された烽燧台の裏側にある岩には、万丈台と書いた大院君の親筆が刻み込まれています。
金海伽倻テーマパーク(김해가야테마파크)
2025-10-23
キョンサンナム道キムヘ市カヤテーマギル161
憩いの場であるとともに多様な文化に接することのできる複合文化スペース。韓国民族の輝かしい遺産である伽倻(カヤ)の歴史を、遊び・体験・展示を通して、見て・聞いて・触って学ぶことのできる、エデュテインメント(Education+Entertainment)体験型テーマパークです。
巫女島・仙遊島(무녀도‧선유도)
2024-04-08
チョンブク特別自治道クンサン市オクト面
巫女島(ムニョド)
巫女島(ムニョド)は群山市から南西に50.8キロメートル離れた海上に位置し、仙遊島(ソニュド)・新侍島(シンシド)・壮子島(チャンジャド)などとともに、古群山(コグンサン)群島を形成しています。面積は1.75平方キロメートル、海岸線の長さは約11.6キロメートルで、現在、仙遊島を中心に、巫女島ー仙遊島、 仙遊島ー壮子島、壮子島ー大壮島の間に橋が架けられているため、一つの島のように歩いて渡ることができます。南西に巫女峰(131メートル)があるだけで、広い地域にそれほど高い山はないというのが特徴です。
仙遊島(ソニュド)
群山港から約50キロメートル離れている仙遊島は約20の島からなる古群山群島の中央に位置しています。西海岸で最も人気の高い避暑地の一つでもあります。
仙遊島と周辺の島々を旅行するときに拠点となるのは仙遊島のチンリ村です。「明沙十里(ミョンサシムニ)」とも呼ばれる仙遊島海水浴場と接しており、村からは馬耳山のようにそびえ立つ望主峰(マンジュボン)がくっきりと見えます。学校、民宿、食堂、自転車レンタル店、ショップ、カラオケ、キャンプ場などが集まっており、シーズンには村全体が賑やかになります。
仙遊島には「仙遊八景」があります。中でも最高の絶景の望主峰は仙遊島のシンボルといえます。頂上に立つと仙遊島周辺の島や海、明沙十里海水浴場と並んで、海上に舞い降りた雁のような形の「平沙落雁」の全景もすべて眺望することができます。美しいという言葉だけでは言い表せない雄大な景色の夕日は、望主峰の頂上だけでなく、仙遊島海水浴場のどこからでもその感動的な景色が観賞できます。



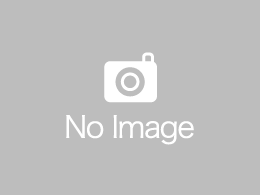
 日本語
日本語
 한국어
한국어 English
English 中文(简体)
中文(简体) Deutsch
Deutsch Français
Français Español
Español Русский
Русский